Masakiです。
「Webライターという働き方に興味があるけれど、未経験からどう始めればいいか分からない」
「Webライターの実際の収入はどれくらいで、本当に生活できるレベルまで稼げるのか不安だ」
「WebライターとWebデザイナー、どちらが自分に合っているか迷っている」
この記事は、あなたが抱えるWebライターに関するそれら全ての疑問に答える、網羅的なガイドです。
未経験からの具体的な始め方、国内外のリアルな収入事情、高単価案件を獲得するための専門スキル、そして「やめとけ」と言われる現実的な理由まで徹底的に解説します。
この記事を読めば、Webライターとしての一歩を踏み出すための、明確なロードマップが手に入ります。

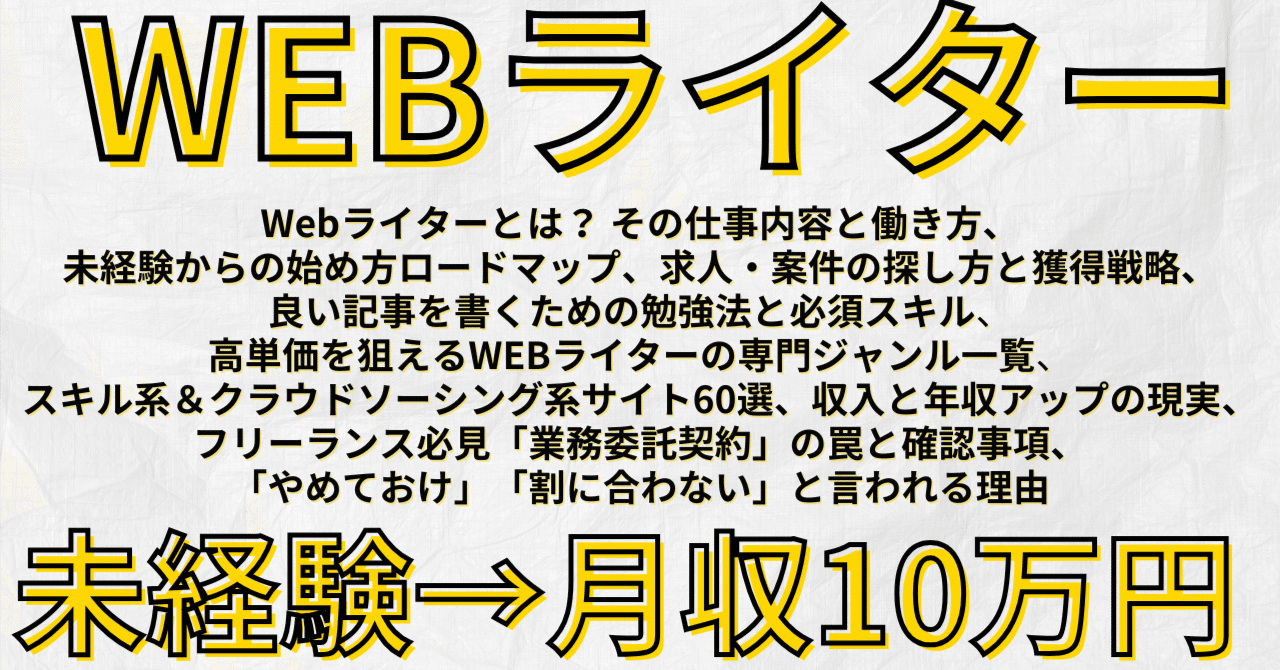
Webライターとは? その仕事内容と働き方の全貌
Webライターとは、その名の通り、主にWeb(インターネット)上に掲載されるコンテンツや文章を作成する仕事です。
しかし、その業務内容は単に「文章を書く」だけにとどまりません。
現代のWebライターは、Webコンテンツ制作における多様な役割を担う専門職へと進化しています。
Webライターの具体的な仕事内容:執筆だけではない多様な業務
Webライターの基本的な仕事は、クライアント(依頼主)の要望に応じた文章を執筆することです。
しかし、実際のプロジェクトでは、以下のような業務も任されることが多くあります。
執筆:記事の本文を作成します。
文章・構成案作成:記事のテーマに基づき、読者の検索意図を満たすための「見出し」や「骨組み」を設計します。
編集・校正:他のライターが執筆した記事を読み、日本語の誤りや情報の正確性をチェックし、より読みやすい文章に修正します。
監修:特定の専門分野(医療、法律、金融など)において、記事内容の専門的な正しさを担保します。
記事の入稿(CMS操作):WordPress(ワードプレス)などのCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を操作し、完成した記事をWebサイトに登録(入稿)する作業です。
画像選定と挿入、サイズ調整:記事の内容に合ったフリー画像を選定し、適切なサイズに調整して記事内に挿入します。
文字の装飾:記事を読みやすくするため、重要な部分の文字に色をつけたり、太さを変えたりする装飾作業です。
取材・インタビュー:専門家や著名人へのインタビュー、またはイベントやセミナーへの参加レポートなど、一次情報を取得して記事を作成します。
特に取材ライティングは、高いコミュニケーションスキルが求められるため、報酬も比較的高めに設定される傾向があります。
このように、Webライターの仕事は多岐にわたり、単なる執筆者(ライター)から、Webコンテンツ制作者(プロデューサー)としての側面も強くなっています。
WebライターとWebデザイナーの違い:どちらを選ぶべきか?
Webライターとよく比較される職業に、Webデザイナーがあります。
どちらもWebコンテンツ制作に不可欠な存在ですが、その役割は根本的に異なります。
Webライターは、主に「テキスト(論理)」を用いて情報を整理し、読者に分かりやすく伝える専門家です。
リサーチ力やSEO(検索エンジン最適化)の知識、論理的な文章構成力が核となるスキルです。
一方、Webデザイナーは、主に「ビジュアル(感覚)」を用いて情報を魅力的に見せ、ユーザー体験を向上させる専門家です。
デザインツール(Figma, Photoshop, Illustratorなど)を扱う技術や、色彩理論、UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)の知識が核となります。
どちらを選ぶべきか迷った場合は、以下の比較表を参考に、自分の適性(論理的思考が得意か、視覚的表現が得意か)を考えてみるとよいでしょう。
| 比較項目 | Webライター | Webデザイナー |
| 主な仕事 | テキストコンテンツ制作 (記事, SEO, 取材) | Webサイトの視覚デザイン (レイアウト, バナー, UI) |
| 核となるスキル | 文章力, リサーチ力, SEO知識 | デザインツール (Photoshop, Figma), デザイン原則, UI/UX知識 |
| 関連スキル | CMS入稿, 画像選定, 取材 | (コーディング: HTML/CSS, JavaScript) |
| キャリアパス | 編集者, コンテンツディレクター, 専門ライター | アートディレクター, UI/UXデザイナー, フロントエンドエンジニア |
| 思考の傾向 | 論理的(情報を整理し、分かりやすく伝える) | 視覚的・感覚的(情報を魅力的に見せる) |
近年では、Webライターが画像選定やCMS入稿を行うように、両方の領域にまたがる業務も増えています。
両方のスキルを持てれば市場価値は飛躍的に高まりますが、初心者はまず、どちらかの核となるスキルを深めることから始めるのが賢明です。
Webライターの多様な働き方:フリーランス、正社員、副業
Webライターとしてのキャリアパスは、一つではありません。
一般的に「フリーランス」のイメージが強いかもしれませんが、実際には「企業で働く」という安定した選択肢も多く存在します。
企業に勤めてライティングを担当する(正社員・契約社員・派遣)
出版社やWeb制作会社、あるいは自社メディアを運営する事業会社のコンテンツマーケティング部門などに、正社員や契約社員として所属する働き方です。
最大のメリットは、収入が安定しやすい点です。
フリーランスのような成果報酬(記事単価)ではなく、時給制や月給制で給料が支払われるため、毎月安定した収入を得ることができます。
後述する求人情報でも示す通り、横浜、東京、大阪などの都市部を中心に、「Webライター 正社員」の募集は多数存在し、未経験から研修制度付きで募集している企業も少なくありません。
安定した環境でスキルを磨きたい人、チームで働きたい人に適しています。
フリーランス(業務委託)として働く
企業や個人から「業務委託」という形で仕事を受注し、成果物(記事)を納品して報酬を得る働き方です。
最大のメリットは、働き方を自由にデザインできる点です。
成果物さえ納期までに納品すれば、いつ、どこで働いても基本的に自由です。
Webライターを副業として本業と両立させたい人や、家事や育児の合間に自宅で仕事をしたい人にとって、非常に魅力的な選択肢です。
副業・在宅アルバイトとしてのWebライター
正社員とフリーランスの中間に位置する働き方です。
企業とアルバイト・パート契約を結び、時給制で働くケースです。
求人サイトでは「フルリモートOK」「週2日、1日3時間から」といった柔軟な条件での募集も多く見られ、副業や主婦(主夫)のニーズに応える形で普及しています。
【完全ロードマップ】未経験からWebライターになるための「丁寧な」始め方
Webライターの仕事は、特別な資格が必須ではないため、未経験からでも独学でスタートすることが可能です。
ここでは、全くの初心者がWebライターとして最初の一歩を踏み出すための、具体的かつ丁寧な7つのステップを解説します。
Webライターの始め方:独学での7ステップ
独学でWebライターを目指すための、最も現実的で効率的なロードマップです。
ステップ1:必要な機材を準備する(パソコン、iPad、スマホ)
Webライターの仕事を始めるにあたり、まず機材を準備する必要があります。
結論から言えば、本気でWebライターを職業として目指すなら、パソコン(ノートパソコン)は必須です。
「スマホだけでWebライターになれるか」という疑問を持つ方も多いですが、スマホだけで可能な仕事は、アンケートへの回答や商品の口コミ・レビューといった、単価が非常に低い「タスク案件」が中心です。
本格的な記事執筆(リサーチ、長文作成、CMS入稿など)をスマホだけで行うのは、効率が非常に悪く、現実的ではありません。
Webライターに必要なノートパソコンのスペックは、それほど高いものでなくても構いません。
ただし、複数のWebサイト(情報源)を同時に開いてリサーチしたり、クライアントとZoomなどでWeb会議をしたりする場面を想定すると、メモリは最低でも8GB以上を推奨します。
パソコンの性能は日進月歩であり、中古品は当たり外れが大きいため、新品での購入が安心です。
また、iPadでの執筆も不可能ではありません。
パソコンに比べて安価で持ち運びやすいメリットはありますが、画面が小さいためリサーチに不便であったり、WordPress(CMS)がうまく機能しなかったりするデメリットも存在します。
もしiPadを選ぶ場合は、作業効率を考慮し、11インチ以上のモデルと、外付けキーボードを必ず一緒に購入しましょう。
ステップ2:Webライティングの基礎スキルを学ぶ
機材を準備したら、Webライティングの基本的なスキルを学びます。
具体的には、基本的な文章スキル(正しい日本語、読みやすい構成)や、SEOの基礎知識、リサーチの方法などです。
詳細な勉強法については、後のセクションで詳しく解説します。
ステップ3:クラウドソーシングサイトに登録する
基礎を学んだら、いよいよ仕事を探すためにプラットフォームに登録します。
初心者が最初に登録すべきは、案件数が豊富で初心者向けの募集も多い「クラウドワークス」や「ランサーズ」といった大手クラウドソーシングサイトです。
例えば、クラウドワークスでの始め方の流れは以下の通りです。
1.クラウドワークスに無料登録する。
2.プロフィールを整える(自己PR、経歴、スキルなどを入力)。
3.仕事を探す(「ライティング」「記事作成」「初心者OK」などで検索)。
4.気になる仕事に応募する(「提案文」を送信)。
5.クライアントと契約し、クライアントが「仮払い」を完了する。
6.指示(マニュアル)に従って記事を執筆する。
7.記事を納品し、クライアントの検収が完了すると報酬が支払われる。
クラウドワークスを推奨する理由として、初心者OKの案件が豊富なこと、実績がプロフィールに蓄積され、次の案件獲得に有利になること、そして「仮払い」システムにより報酬が支払われないリスクが極めて少ないことが挙げられます。
また、クラウドワークスでは「WEBライター検定3級」に無料で挑戦でき、合格すればプロフィールに表示されるため、スキルの証明にもなります。
ステップ4:プロフィールとポートフォリオを作成する
クラウドソーシングサイトに登録したら、案件に応募する前に、必ずプロフィールを充実させましょう。
クライアントは、あなたのプロフィールを見て、仕事を任せるかどうかを判断します。
特に重要なのが「ポートフォリオ」(あなたの実績やスキルを示す作品集)です。
未経験者には実績がありませんが、「サンプル記事」を自分で作成してポートフォリオとして提示することが、案件獲得の鍵となります。
ポートフォリオの具体的な作り方は、後のセクション(<h2>Webライターの求人・案件の探し方)で詳述します。
ステップ5:初心者向けの案件に応募する
プロフィールとポートフォリオ(サンプル記事)が準備できたら、いよいよ案件に応募します。
最初は「初心者OK」「未経験者歓迎」と記載されている案件から挑戦しましょう。
ここで非常に重要な戦略があります。
それは、報酬の単価(例:文字単価0.5円)だけで案件を選ばないことです。
初心者が最も重視すべきは、「フィードバック(添削)あり」と記載されている案件です。
クライアントからの具体的な添削や修正指示は、本で学ぶよりも遥かに実践的なスキルアップにつながります。
報酬をもらいながら、プロの編集者から実質的に無料のトレーニングを受けられる機会だと捉えましょう。
ステップ6:記事を執筆し納品する
契約が成立したら、クライアントから渡される指示書(マニュアル、レギュレーション)を熟読し、それに従って記事を執筆します。
納期を守ることはもちろん、誤字脱字がないか、指示されたルール(例:「です・ます」調で統一、など)が守れているかを何度も確認してから納品します。
ステップ7:フィードバックを受け改善する
納品後、クライアントから修正の依頼やフィードバックが来ることがあります。
特に初心者のうちは、多くの修正が入るのが普通です。
落ち込む必要はなく、むしろ「どこがダメだったのか」を具体的に教えてもらえる絶好の学習機会です。
クライアントからのフィードバックを真摯に受け止め、次回の記事に活かすことで、スキルは飛躍的に向上します。
クラウドソーシングでは、納品後にクライアントとワーカーがお互いを評価します。
常に「評価5」を目指して真剣に取り組む姿勢が、次の継続案件や新規案件の獲得に直結します。
Webライターの始め方:主要プラットフォーム別(note, YouTube)
クラウドソーシング以外にも、Webライターとしてのキャリアをスタートさせるために活用できるプラットフォームがあります。
noteの活用法
ブログサービスの「note」は、Webライターの「始め方」において非常に有効なツールです。
noteは手軽に自分の文章を公開できるため、ステップ4で解説した「ポートフォリオ」として最適です。
自分の得意ジャンルについて、SEOや読者のニーズを意識した記事をnoteで執筆・公開し、その記事URLをポートフォリオとしてクライアントに提示することで、文章スキルを具体的に証明できます。
YouTubeの無料解説動画の活用法
YouTubeには、Webライターの始め方や稼ぎ方を解説する無料の動画が数多く存在します。
Webライターとブログ運営は重なるスキルが多く、相乗効果が高いとされています。
ブログでライティングスキルを磨きながら、Webライターとして(最初は低単価でも)報酬を得て実績を積む、という両輪で進める戦略が推奨されています。
Webライターになるには:ブログ運営は必要か?
結論から言うと、ブログ運営はWebライターになるために必須ではありませんが、運営することを強く、強く推奨します。
ブログは、Webライターにとって「練習」「ポートフォリオ」「営業ツール」の3つの役割を同時に果たしてくれる、最強の武器となり得ます。
ブログがポートフォリオになる仕組み
クライアントがライターを選ぶ際、最も知りたいのは「この人はどれくらいの品質の記事が書けるのか」という点です。
あなたのブログは、あなたのライティングスキル、SEO知識、リサーチ力、そして専門性を一覧できる「生きた実績」そのものになります。
ブログで執筆した記事、特に検索順位で上位表示されたり、多くの人に読まれたりした人気記事をクライアントに見せることで、あなたは「スキルを証明できるライター」として高い評価を得ることができ、案件獲得に直結します。
ブログで何を書くべきか?(ジャンルの選定)
では、Webライターがポートフォリオとしてブログを運営する場合、何を書けばよいのでしょうか。
最も重要なのは、「あなたの得意ジャンル」で書くことです。
「得意ジャンル」とは、あなたの「経験(Experience)」が活きるジャンルのことです。
例えば、あなたが看護師であれば医療や健康について、保育士であれば保育や子育てについて、転職を3回経験しているのであれば転職ノウハウについて、といった具合です。
Googleが記事の品質を評価する基準である「E-E-A-T」(経験・専門性・権威性・信頼性)においても、「経験」は非常に重視されています。
あなたの実体験に基づいた記事は、AIや他のライターには書けない独自の価値を持ちます。
ブログであなたの専門性を発信することは、Webライターとして高単価案件を獲得するための「専門特化」戦略の第一歩にもなるのです。
Webライターの勉強法と必須スキル:良い記事を書くために
Webライターとして継続的に案件を獲得し、収入を上げていくためには、スキルアップが不可欠です。
「良い記事を書くため」に必要なスキルと、その具体的な勉強法を解説します。
Webライターに必要な6つのコアスキル
単に文章が書けるだけでは、高単価ライターにはなれません。
現代のWebライターには、以下の6つのコアスキルが求められます。
スキル1:基本的な文章力と日本語力
Webライターとしての基礎中の基礎となる能力です。
誤字脱字をなくすことはもちろん、日本語の文法や表現を正しく使いこなす能力が求められます。
Webコンテンツは不特定多数の読者が読むため、誰が読んでも理解できる、分かりやすく簡潔な表現を心がけることが重要です。
スキル2:圧倒的なリサーチ力
記事の品質は、リサーチの質で9割決まると言っても過言ではありません。
クライアントの指示や読者の検索意図の背景にある「本当の悩み」を深く掘り下げるリサーチ力が求められます。
優れたリサーチとは、単に情報を集めることではありません。
まず、「この記事の読者は誰か?」「その読者のどんな悩みを解決するのか?」そして「その課題を解決するために、この記事で何を伝えるべきか?」という3点を明確に定義することから始まります。
情報源としては、個人のブログや匿名の掲示板ではなく、官公庁(国)や大手企業が発表している統計データ、信頼できる研究機関の論文など、一次情報や信頼性の高い情報源を使うことが重要です。
学術論文を検索できる「Google Scholar」などのツールを活用し、記事に客観的な根拠(エビデンス)を盛り込むことで、記事の信頼性(E-E-A-T)は飛躍的に高まります。
そして、リサーチが重要で複雑なジャンル(金融、医療など)は、必然的に文字単価が高くなる傾向があります。
リサーチ力が高いライターは、文字単価2.5円を超えるような高単価案件でも重宝され、クライアントから手放されない存在となります。
スキル3:SEO(検索エンジン最適化)の知識
Webライター、特に検索結果からの流入(オーガニックトラフィック)を目的とする「SEOライター」にとっては、必須のスキルです。
SEOとは、Googleなどの検索エンジンで、特定のキーワードで検索した際に、記事を上位に表示させるための技術や戦略のことです。
かつては「記事内にキーワードをたくさん詰め込む」といった単純なテクニックが主流でしたが、現代のSEOは遥かに高度化しています。
現代のSEOライティングで求められるのは、以下のようなスキルです。
検索エンジンアルゴリズムの理解(Googleが何を「良い記事」と判断するかの理解)。
キーワードリサーチ能力(読者がどんな言葉で検索しているかを見つける力)。
データ分析(記事公開後、オーガニックトラフィック、CTR(クリック率)、直帰率などのデータを分析し、改善する力)。
ユーザーの検索意図(インテント)を完璧に満たすコンテンツ戦略。
E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の担保。
これらのスキルは、単なる「ライター」を超え、「SEOエキスパート」や「コンテンツストラテジスト(戦略家)」としての領域であり、グローバル基準で見ても、高単価なSEO専門家の必須スキルとされています。
スキル4:構成案を作成する能力
リサーチに基づき、読者の疑問や悩みを解決するための「記事の設計図(構成案)」を作成するスキルです。
優れた構成案は、記事の品質を担保し、読者を満足させる道筋を示します。
この構成案作成スキルがあれば、単なる執筆者(ライター)から、記事全体の品質管理やライターの管理を行う「編集者」や「ディレクター」へとキャリアアップする道も開けます。
スキル5:クライアントの意図を汲み取る読解力
Webライターの仕事は、クライアントから提供されるマニュアルや指示書(レギュレーション)に従って行われます。
このレギュレーションを正確に読み取り、遵守する能力(読解力)が非常に重要です。
レギュレーションが守られていない記事は、クライアントからの信頼を失い、多くの修正(手戻り)が発生します。
修正に時間がかかれば、それだけ自分の時給は下がり、「割に合わない」仕事になってしまいます。
スキル6:継続したスキルアップと学びの姿勢
Webライターとして成功し続けるためには、日々のスキルアップが欠かせません。
特にSEOのトレンドやGoogleのアルゴリズムは、日々刻々と変化しています。
他の成功しているライターの記事を読んで自分の書き方を研究したり、新しい分野に挑戦して知識を広げたりするなど、継続的に学び続ける姿勢が、クライアントから常に期待される存在であり続けるための鍵となります。
Webライターの独学勉強法7選
これらのスキルを身につけるための、独学で可能な7つの勉強法を紹介します。
勉強法1:Webライティング関連の本を読む
体系的な知識をインプットするために、書籍は非常に有効です。
特にSEOやライティングの「原理原則」を学ぶことは、変化の激しいWeb業界において強力な土台となります。
以下に、WebライターやSEO担当者から広く推奨されている定番の書籍を紹介します。
SEO基礎(初心者向け)
『いちばんやさしい新しいSEOの教本』:SEOの全体像を対話形式で学べる入門書です。

『10年使えるSEOの基本』:小手先のテクニックではなく、Googleの理念に基づいた普遍的なSEOの考え方を学べます。
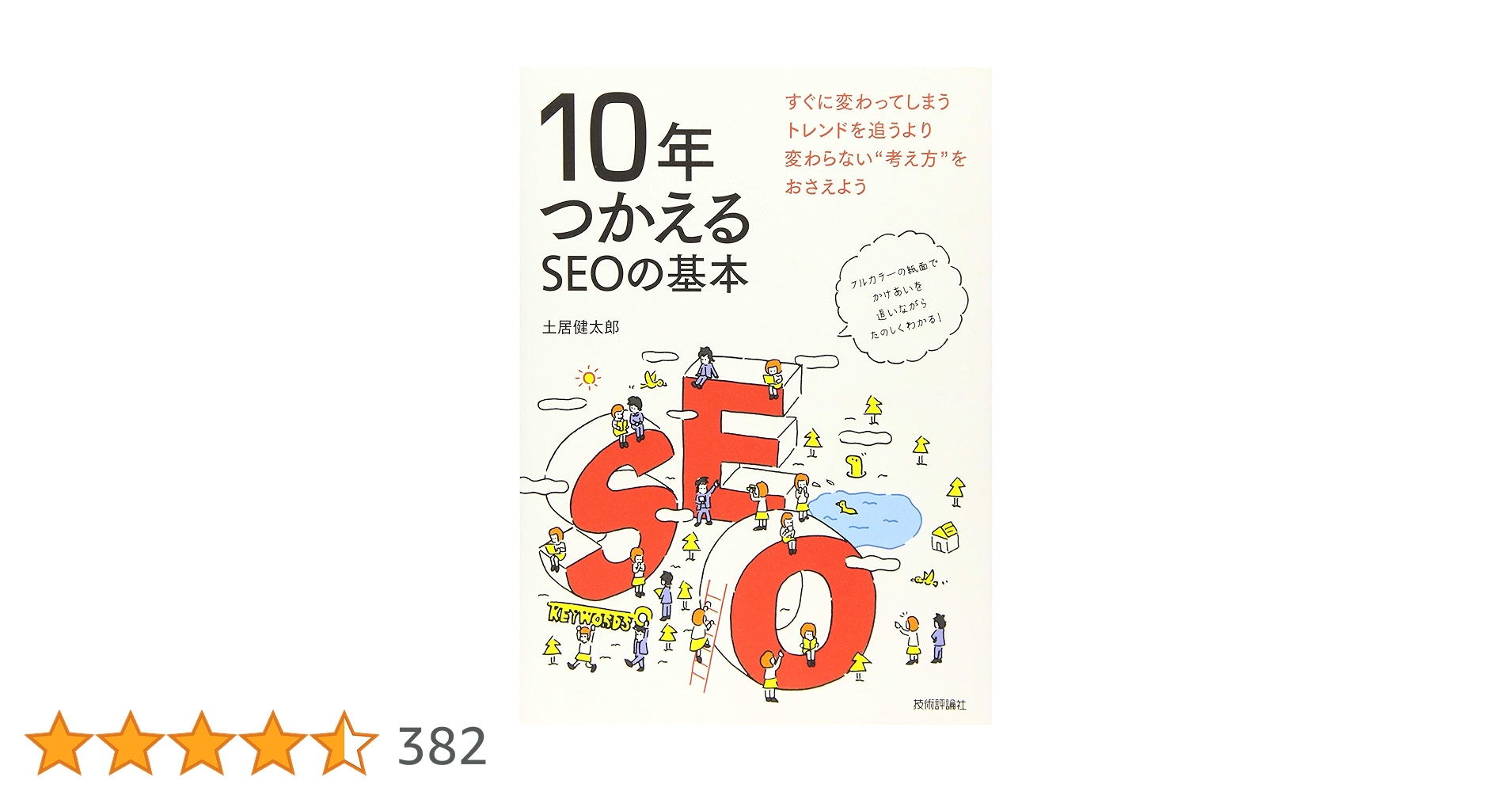
SEOライティング特化
『SEOに強い Webライティング 売れる書き方の成功法則64』:具体的なライティングテクニックが網羅されています。
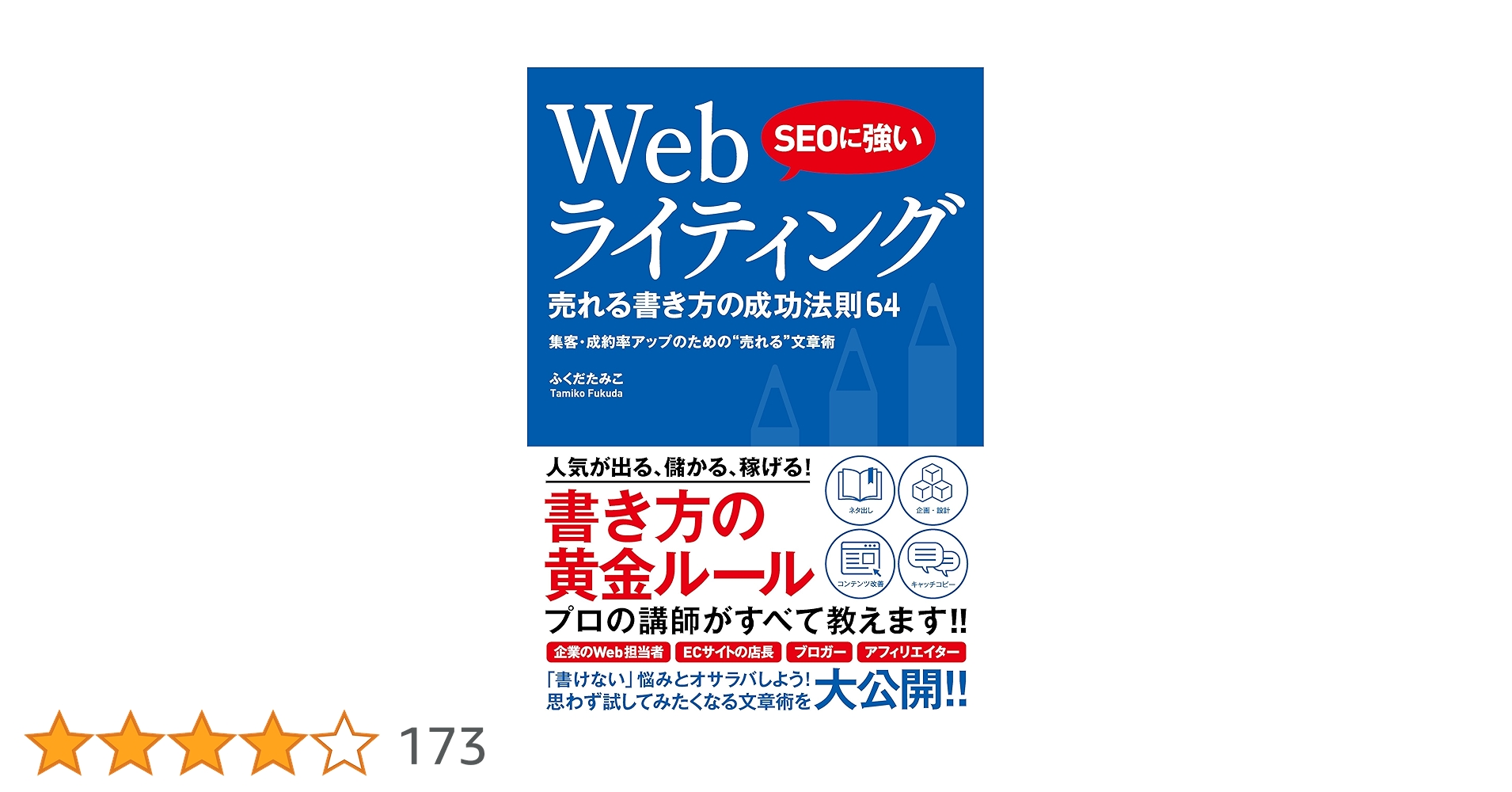
『沈黙のWebライティング』:ストーリー形式でSEOライティングの本質を学べる名著です。

『入門SEOに効くWebライティング』:Webライティングを1から学ぶ人向けに、執筆から編集、分析までを解説しています。

SEO技術(中級者向け)
『現場のプロから学ぶ SEO技術バイブル』:SEOの専門知識を網羅的に学べる、より技術的な内容です。
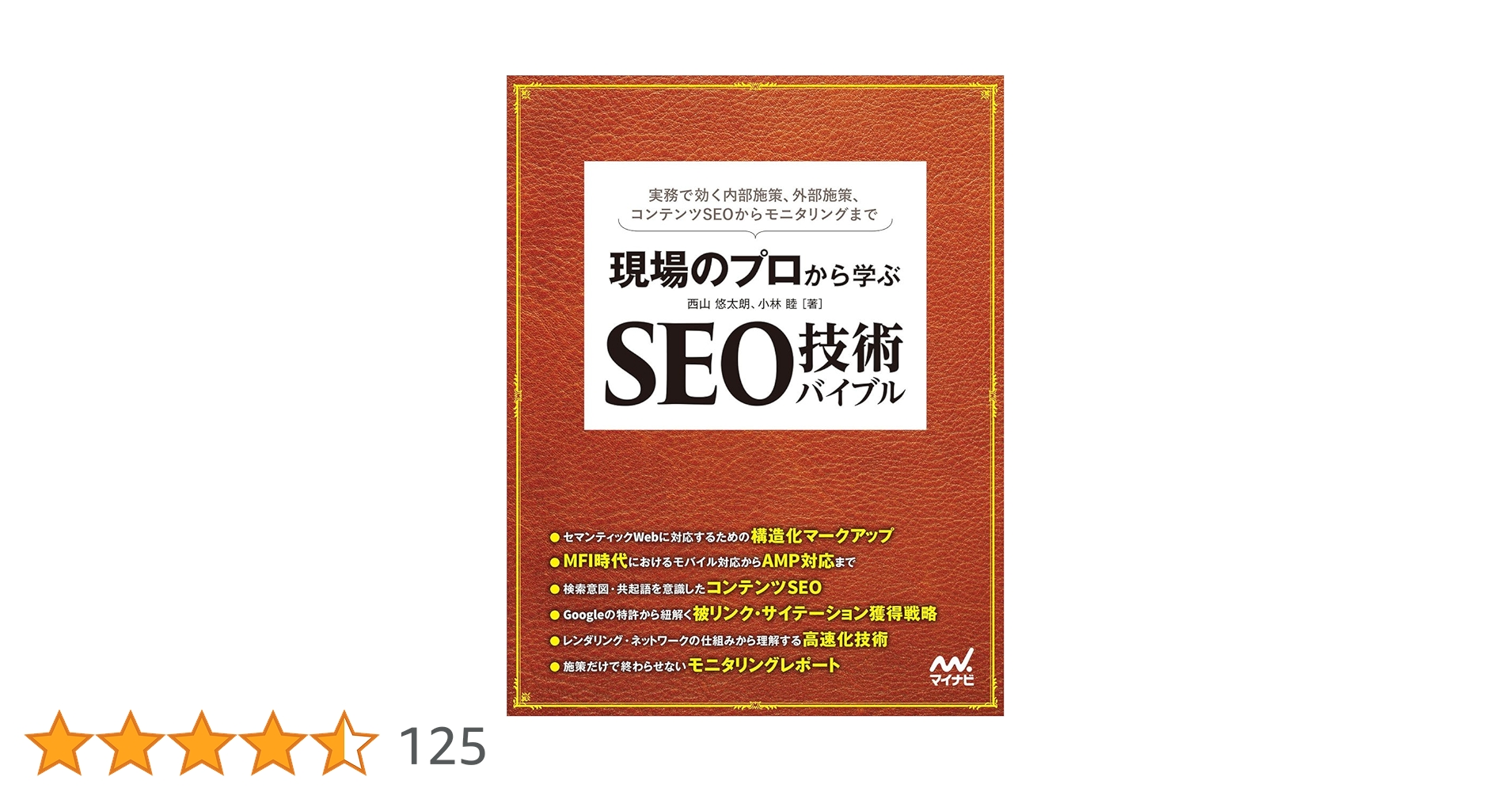
『これからのSEO内部対策 本格講座』:内部対策について詳細に解説されています。
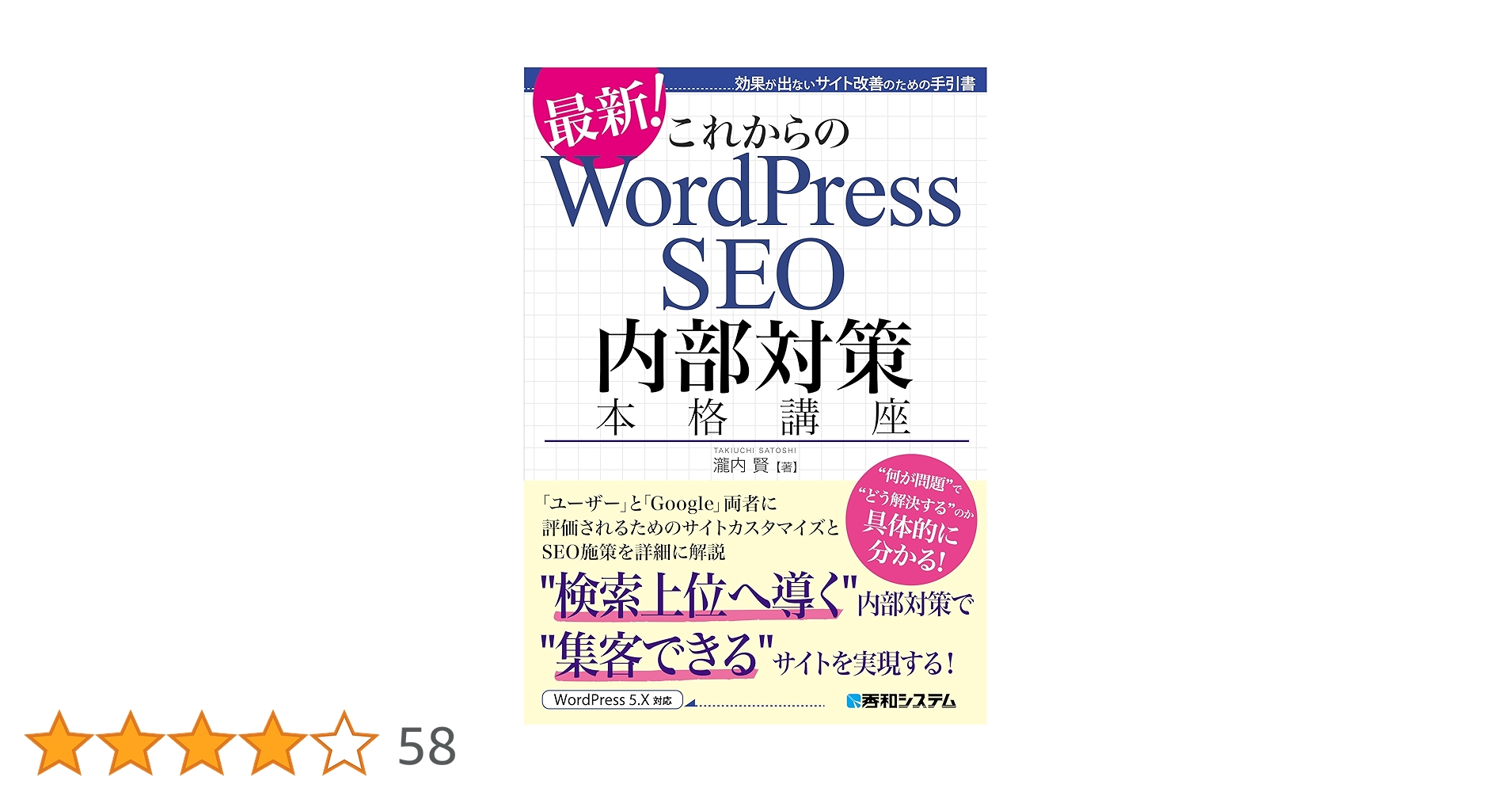
勉強法2:良い記事の「写経」で型を学ぶ
「写経」とは、自分が「読みやすい」と感じる記事や、目標とするライターの記事を、そのまま一字一句書き写す練習方法です。
この練習の目的は、「書き写すこと」自体ではありません。
何も考えずに書き写すだけでは、単なるタイピング練習になってしまいます。
写経の本質は、「なぜ、この書き手はここで改行したのか?」「なぜ、この句読点(、)を入れたのか?」「なぜ、この語尾を選んだのか?」といった、書き手の「意図」を考察しながら書き写すことです。
これにより、読みやすい文章の「型」や「リズム」を、感覚的に身につけることができます。
ただし、写経した文章をそのままコピー&ペーストして自分の記事として公開することは、著作権の侵害にあたるため、絶対に行ってはいけません。
勉強法3:ブログを運営し実践する
ロードマップのセクションでも述べた通り、ブログ運営は最強のアウトプット(実践)の場です。
本(勉強法1)で学んだSEOやライティングの知識を、自分のブログで実際に試し、試行錯誤することで、スキルは定着します。
さらに、それがそのままポートフォリオ(実績)にもなります。
勉強法4:実際の案件でクライアントから学ぶ
最も効果的で実践的な学習方法は、実際の案件を受注し、執筆しながら学ぶことです。
特に、クライアント(編集者)から受ける「添削(フィードバック)」は、独学では気づきにくい自分の文章の弱点や、読者ニーズの把握の甘さを教えてくれる、最高の教材となります。
勉強法5:Webライター向けメディアやSNSで情報収集する
Webライター向けのノウハウを発信しているWebメディアや、X(旧Twitter)などで現役のWebライターや編集者の発信をフォローすることで、最新のSEOトレンドや案件情報を収集できます。
勉強法6:資格を取得する(Webライター検定、SEO検定など)
資格取得は、知識を体系的に学ぶ良い機会となります。
例えば、クラウドワークスが提供する「WEBライター検定3級」は、無料で挑戦できます。
この検定の対策講座(YouTubeの限定公開動画)は、ライティングの要点が網羅されており、学習効果が高いと評価されています。
合格すれば、あなたの基礎スキルを客観的に証明する材料にもなります。
勉強法7:オンラインコミュニティへの参加
独学は孤独であり、モチベーションの維持が難しい場合があります。
Webライター向けのオンラインコミュニティやサロンに参加し、他のライターと交流することで、情報交換やモチベーション維持に役立ちます。
Webライタースクールや講座は必要か? 独学との徹底比較
「Webライター スクールは必要なのか?」これは多くの初心者が悩むポイントです。
結論から言うと、スクールは必須ではありませんが、特定の目的を持つ人にとっては有効な選択肢となります。
Webライタースクールのメリット
Webライタースクールや有料講座の最大のメリットは、「添削指導」が受けられる点です。
独学では「自分の文章のどこが悪いのか」を客観的に判断するのが難しいですが、プロの講師から直接フィードバックをもらうことで、弱点を効率的に修正できます。
また、知識を体系的に学べること、営業や提案文の書き方まで指導してもらえること、場合によってはスクール経由で案件を紹介してもらえる(コネクションができる)こともメリットです。
Webライタースクールのデメリット
最大のデメリットは、当然ながら「費用が高い」ことです。
独学であれば、書籍代の1万円以内で学習をスタートできますが、スクールや講座は数万円から、マンツーマン指導などでは数十万円の費用がかかります。
独学とスクール、どちらが優れているかではなく、あなたの目的や予算、学習スタイルに合わせて選ぶことが重要です。
| 比較項目 | 独学 (本・ブログ・YouTube) | スクール (講座) |
| メリット | 費用が安い (1万円以下), 自分のペースで学べる | 知識を体系的に学べる, 添削指導がある, 営業・提案の仕方も学べる, 人脈/案件紹介の可能性 |
| デメリット | 挫折しやすい, 自分の弱点に気づきにくい (添削がない), 案件獲得は自力 | 費用が高い (数万〜数十万), 時間的拘束 |
| 費用目安 | 1万円以内 (書籍代など) | 24,000円 (ユーキャン) 〜 数十万円 |
| おすすめな人 | 独学継続力がある人, 低コストで始めたい人, 自分の経験を活かせる専門分野が明確な人 | 最短でスキルを習得したい人, プロの添削が欲しい人, 継続できるか不安な人 |
ユーキャンのWebライター講座の評判と費用
有名な「ユーキャン」にもWebライター講座があります。
費用は一括払いで 24,000円(税込)、または月々2,750円の9回払いです。
1ヶ月でWebライターのスタートラインに立つことを目指すカリキュラムとなっています。
口コミや評判としては、「独学に比べて費用が高い」という意見や、「料金が高い割に内容が基礎的すぎる」「受講しても仕事にありつけない」といったネガティブな評価も見られます。
一方で、基礎を体系的に学ぶ入り口としては機能しているようです。
Webライターの求人・案件の探し方と獲得戦略
スキルを学んだら、次は実践の場、つまり「仕事(案件)」を探します。
多くの人が「Webライター=フリーランス」と考えがちですが、実際には「正社員」や「アルバイト」といった安定した雇用形態の求人も豊富に存在します。
ここでは、Webライターの多様な案件の探し方と、採用率を劇的に上げるための戦略を解説します。
Webライターの案件はどこで探す? 11の探し方
Webライターが仕事を探す方法は、主に以下の11のルートがあります。
1.クラウドソーシングサイトを利用する(クラウドワークス、ランサーズなど):初心者が最初に利用する王道ルートです。
2.求人検索サイトで検索する(Indeed, スタンバイ, 求人ボックスなど):正社員、アルバイト、業務委託まで、あらゆる雇用形態の募集が見つかります。
3.フリーランスエージェントに登録する(レバテックフリーランス、クラウドテックなど):高単価な非公開案件を紹介してもらえる可能性がありますが、中級者以上向けが多いです。
4.SNS(X/Twitter)から応募する:「#Webライター募集」「#ライター募集」などのハッシュタグで検索します。
5.メディアへ直接営業を行う:自分が書きたいと思うWebメディアの運営会社に、直接「記事を書きませんか」と営業をかけます。
6.SEO会社や記事制作会社の募集を確認する:多くの制作会社が、ライターを常時募集しています。
7.マッチングサイトに登録しておく:ライターを探している企業とマッチングできるサイトに登録します。
8.ポートフォリオになるブログを作る:あなたのブログを見た企業側から「スカウト」が来るケースです。
9.交流会や紹介で受注する:ライター仲間や異業種交流会での人脈から仕事につながります。
10.Webライター専用転職エージェントに登録する:正社員としての転職を目指す場合に利用します。
11.Webライティングの講座を受講する:講座の運営元から案件を紹介してもらえる場合があります。
【雇用形態別】Webライターの求人動向
ここでは、特に検索ニーズの高い「完全在宅・未経験」「正社員」「アルバイト」の求人動向を、具体的なデータを交えて解説します。
「完全在宅」「未経験OK」の求人実態
「未経験から、完全に在宅で働きたい」というニーズは非常に高いですが、そのような求人は実際に多数存在します。
求人サイトでは「完全リモートワークOK」「未経験者歓迎」「研修制度でしっかりスキルアップ」といった求人が、正社員、業務委託、アルバイト・パートなど多様な雇用形態で見つかります。
「未経験OK」は「スキル不要」という意味ではなく、「ポテンシャル(学ぶ意欲)があれば研修で育成します」という企業側の意思表示であることが多いです。
業務委託(フリーランス)向けの案件では、時給1,500円のWEBメディアライターや、月給30万円〜48万円が目安の求人広告コピーライターといった募集例があります。
「アルバイト・パート」の求人
副業や、家事・育児と両立したい主婦(主夫)層には、アルバイト・パート形態も人気です。
「フルリモート(完全在宅)」の募集も多く、時給1,250円〜1,500円程度が相場となっています。
中には「週1日1時間〜OK」や「1日3時間〜相談可能」といった、非常に柔軟なシフトに対応している求人もあり、ライフスタイルに合わせて働きやすい環境が整いつつあります。
【重要】案件獲得率を劇的に上げるポートフォリオの作り方
あなたが正社員に応募するにせよ、フリーランスの案件に応募するにせよ、採用率を左右する最も重要なツールが「ポートフォリオ」です。
ポートフォリオとは何か? なぜ必要か?
ポートフォリオとは、あなたの「スキル」と「実績」を証明するための「作品集」です。
あなたが「Webライターです」と名乗っても、クライアントはあなたがどれほどの文章力を持ち、どんなジャンルに詳しいのか判断できません。
そこで、ポートフォリオ(過去に執筆した記事や、自分で用意したサンプル記事)を見せることで、あなたの実力を客観的に証明するのです。
特に未経験者の場合、実務経験(実績)はゼロです。
しかし、「サンプル記事」を用意してポートフォリオとして提示しなければ、クライアントは判断材料が何もないため、あなたを採用することができません。
実績ゼロの初心者でも、サンプル記事を活用して自分の強みをアピールし、案件を獲得した例は多数あります。
ポートフォリオに載せるべき7項目
ポートフォリオは、単に記事を並べるだけでは不十分です。
クライアントが知りたい情報を網羅した「営業資料」として作成する必要があります。
自己紹介:あなたが誰であるか、簡潔な挨拶。
経歴・保有資格:信頼性や専門性を担保する情報(例:看護師免許、ファイナンシャルプランナー級、〇〇業界で5年勤務、など)。
経験・趣味:得意ジャンルにつながるパーソナルな経験(例:3度の転職経験、双子の子育て経験、ブログ月間1万PV運営、など)。
得意ジャンル・執筆実績(サンプル記事):最も重要。
ここで実際の記事を見せます。
業務の対応範囲:執筆のみか、構成案作成、WordPress入稿、画像選定まで可能か。
参考単価:希望する文字単価や記事単価、時給の目安。
連絡先:メールアドレスや、WordPressで作成した場合は「お問い合わせフォーム」を設置します。
実績ゼロの初心者が用意する記事サンプル(記事例)
未経験者にとってのポートフォリオの核は、「サンプル記事」です。
何を書けばよいかというと、あなたの「得意ジャンル」や、応募したい案件のジャンルに関連する記事です。
例えば、看護師の経験を活かしたいなら「看護師の転職失敗例」について、保育士の経験を活かしたいなら「保育園でのイヤイヤ期対応」について、といった具合です。
記事の構成は、「タイトル」「導入文(読者が得られるメリット)」「本文(複数の見出しで構成)」「まとめ(行動喚起)」という、Web記事の基本の型に沿って執筆します。
なお、過去にクラウドソーシングなどで納品した記事をポートフォリオとして公開する場合、著作権はクライアントに譲渡しているケースがほとんどです。
クライアントの許可なく無断で公開することは契約違反や著作権侵害にあたる可能性があるため、必ず事前に許可を取りましょう。
許可が取れない場合は、新たにサンプル記事を書き下ろすのが安全です。
採用率を上げる3つのポイント
募集内容を徹底的に読み込む:クライアントが何を求めているかを正確に把握し、その要求に応える提案をすることが最も重要です。
誤字脱字をチェックしてから提出する:ライターとしての最低限の信頼性です。
誤字脱字の多い提案文は、その時点で見送られます。
プロフィールとポートフォリオを充実させておく:提案文は、プロフィールやポートフォリオとセットで見られます。
初心者がやりがちなNGな提案文
100%コピペの使い回し:どの案件にも同じ内容を送っている提案文は、クライアントにすぐに見抜かれ、熱意がないと判断されます。
募集者の質問を無視した内容:募集要項を読んでいない証拠であり、即不採用となります。
「初心者アピール」が強い:「初心者ですが、一生懸命頑張ります」といった熱意だけのアピールは、クライアントには響きません。
「未経験ですが、〇〇の資格(経験)があり、この分野で貢献できます」と、具体的なメリットを提示する必要があります。
誤字脱字が多い、文章が読みにくい:ライターとして致命的です。
【要注意】初心者が避けるべき「割に合わない」案件の特徴
初心者のうちは、案件を獲得することに必死になりがちですが、中には避けるべき「割に合わない」案件も存在します。
特徴1:文字単価が極端に低い案件
文字単価0.5円未満、特に0.1円などの案件は、執筆にかかる労力に見合わない可能性が高いです。
実績作りのために1〜2件受けるのは戦略としてあり得ますが、スキルアップにもつながらない単純作業である場合が多いため、基本的には避けるべきです。
特徴2:クライアントの信頼性が低い(評価が悪い)案件
クラウドソーシングでは、クライアントの過去の評価が見られます。
評価が著しく低い、あるいは「連絡が途絶えた」などの悪いレビューが多いクライアントの案件は、トラブルに巻き込まれる可能性があるため避けましょう。
特徴3:フィードバック(FB)が全くない案件
「納品したら、はい終わり」という、フィードバックが一切ない案件は、一見すると楽に見えます。
しかし、初心者がスキルアップするためには、プロからのFBが不可欠です。
成長を重視するなら、FBがない案件は避けるべきです。
特徴4:マニュアルが異常に複雑、または修正回数が無制限の案件
クライアントの要求が多すぎたり、マニュアルが過度に複雑だったりすると、執筆よりもマニュアルの読解に時間がかかり、時給換算で「割に合わない」仕事になります。
「納得いくまで修正をお願いします」といった、修正回数が無制限の案件も危険です。
特徴5:報酬未払いや音信不通のリスク
SNSのDMなどで直接契約した場合、納品したのに報酬が支払われない、といったリスクがあります。
初心者のうちは、クラウドソーシングの「仮払い」(クライアントが報酬を運営に預け、納品後に支払われる仕組み)制度があるプラットフォームを利用し、リスクを回避しましょう。
Webライターの収入と年収アップの現実
Webライターを目指す上で最も気になるのが「収入」です。
ここでは、Webライターの収入源、単価相場、そして「月収40万」といったレベルを目指すための年収アップ戦略を、国内外のデータに基づいて解説します。
Webライターの収入源と単価の決まり方
Webライターの収入源は、主に「文字単価」または「記事単価」で計算される報酬です。
フリーランスの場合は、このどちらかで受注するケースがほとんどです。
単価がどのように決まるかには、主に3つの要素が関係しています。
1.Webライター自身のスキル:実績、ライティングスキル、SEO知識、専門性など。
2.執筆ジャンルの専門性:専門性が高いジャンルほど、単価は高くなります。
3.クライアントの予算:メディアの運営方針や予算規模によって、支払える単価の上限が決まります。
文字単価 vs 記事単価:どちらが良いか?
初心者のうちは、成果が分かりやすい「文字単価」(例:1文字1円)が好まれます。
一方、「記事単価」(例:1記事5,000円)は、執筆文字数を気にしすぎず、記事の「質」に集中できるメリットがあります。
ただし、記事単価の場合は、想定される文字数を必ず確認する必要があります。
例えば「1記事5,000円」でも、10,000文字の執筆が求められれば、実質的な文字単価は0.5円になってしまいます。
重要な視点:「時給」で考える
Webライターが収入を考える上で、文字単価以上に重要なのが「時給」の視点です。
例えば、以下の2人のライターを比較してみましょう。
Aさん:文字単価2.0円。
3,000文字の記事を5時間かけて執筆。
報酬:6,000円。
時給:1,200円。
Bさん:文字単価1.5円。
3,000文字の記事を2時間かけて執筆(得意ジャンルのため)。
報酬:4,500円。
時給:2,250円。
文字単価はAさんの方が高いですが、時給はBさんの方が圧倒的に高い(稼いでいる)ことが分かります。
収入を上げる本質とは、単に文字単価を上げることではなく、専門性を高めて執筆効率を上げ、「時間単価(時給)」を高めることにあるのです。
Webライターの単価相場:レベル別・ジャンル別
Webライターの単価相場を、ライターのレベル別、そして執筆ジャンル別にまとめます。
| ライターレベル | 文字単価(目安) | 概要 |
| 初級(初心者) | 0.5円~2円 | 実績が少ない。 |
まずは案件をこなすことが目標 |
| 中級 | 2円~5円 | SEOの基本を理解し、一定品質の記事を納品できる |
| 上級(専門家) | 5円~20円以上 | 高い専門性、SEO戦略、取材、監修などが可能 |
| 専門ジャンル | 文字単価(目安) | 必要なスキル・背景 |
| 一般(ライフスタイル等) | 2円~10円 | 基礎的なリサーチ力・文章力 |
| 美容・コスメ | 1円~5円 | 薬機法知識、トレンド理解 |
| 不動産・脱毛 | 4円~ | 専門知識、E-E-A-T(経験) |
| IT・テクノロジー | 5円~15円 | IT業界経験、技術的理解 |
| 金融 (YMYL) | 5円~15円 | 資格(FP等)、E-E-A-T |
| 医療 (YMYL) | 5円~20円 | 資格(医師、看護師等)、E-E-A-T |
| 法律 (YMYL) | 10円~ | 資格(弁護士、税儀師等)、E-E-A-T |
1記事いくら? 案件例と報酬の目安
文字単価ではなく、「1記事あたりいくら」という記事単価での報酬目安は以下の通りです。
まとめ記事(調べれば書ける内容):3,000円~
SEO記事(SEOスキルが必要):3,000円~数万円
インタビュー・取材記事:1万円~3万円
医療系などの専門記事:1万円~10万円
Webライターの生産性:1時間に何文字書ける?
時給を意識する上で、自分が「1時間に何文字書けるか」という生産性を知ることは重要です。
1時間の執筆文字数
これは執筆するジャンルの難易度や、リサーチにかかる時間によって大きく変動します。
一般的には、リサーチと執筆を合わせて、1時間あたり1,000文字~2,000文字程度が一つの目安とされています。
中には、ライトノベルの小説家で平均1時間2,000字というデータや、1時間3,000字を書けないとプロとは言えない、という厳しい意見もあります。
まずは、1時間2,000字の執筆を目指し、タイピング練習やリサーチの効率化を図るとよいでしょう。
1日の執筆文字数と作業時間の目安
Webライターが受注する案件は、1記事あたり3,500〜4,000文字程度の一般的なノウハウ記事が多いです。
もし専業のWebライターとして活動する場合、1日の執筆文字数は8,000文字前後が妥当なラインとされています。
副業として、まず「月収5万円」を目指す場合のシミュレーションをしてみましょう。
目標月収:5万円
想定文字単価:1.0円
月の稼働日数:20日
この場合、50,000円 ÷ 1.0円 = 月に50,000文字の執筆が必要です。
50,000文字 ÷ 20日 = 1日あたり2,500文字の執筆が必要、という計算になります。
Webライターの税金と確定申告:副業・フリーランス必見
Webライターとして収入を得るようになると、フリーランス(個人事業主)であれ、副業であれ、「税金」の問題が必ず発生します。
税金は、稼ぐことと表裏一体の重要な知識です。
副業でも開業届は必要か?
Webライターとして活動を始める際、「開業届」を税務署に提出することは必須ではありません。
しかし、副業であっても開業届を提出(=個人事業主になる)ことには、税制上の大きなメリットがあります。
開業届を出すメリット
青色申告が可能になる:最大のメリットです。
経費の範囲が広がる:仕事で使うパソコン代、通信費、書籍代などを経費として申告しやすくなります。
屋号名義の銀行口座:屋号(ビジネス上の名前)で銀行口座を開設でき、プライベートと事業の収支を明確に分けられます。
開業届を出すデメリット
失業手当が受けられない可能性:会社を辞めた際に受け取れる失業保険(失業手当)の対象外となる可能性があります。
会社に副業がバレる可能性:確定申告により住民税の通知が会社に行くため、副業が禁止されている場合は注意が必要です(ただし、確定申告時に「住民税を自分で納付」を選択すれば回避できる場合が多いです)。
確定申告の手続きが煩雑になる:後述する青色申告は、白色申告に比べて帳簿付けが複雑になります。
青色申告と白色申告の違いとメリット
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
節税のことを考えるなら、開業届と「青色申告承認申請書」を提出して「青色申告」を選ぶ方が圧倒的にお得です。
青色申告の主なメリット
最大65万円の特別控除:売上から経費を引いた「所得」から、さらに最大65万円を差し引くことができます。
(例:所得100万円の場合、課税対象は35万円となり、税金が大幅に安くなります)。
赤字を3年間繰り越せる:事業が赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。
30万円未満の固定資産を一括で経費にできる:通常、10万円以上のパソコンなどは「減価償却」として数年に分けて経費化しますが、青色申告なら30万円未満まで一括でその年の経費にできます。
青色申告(65万円控除)を行うには、「複式簿記」という複雑な帳簿作成が必要ですが、これは「freee」や「マネーフォワード」などの会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても対応可能です。
確定申告のポイント
正社員やパート(給与所得者)が副業でWebライターを行い、その「所得」(売上から経費を引いた額)が年間で20万円を超えた場合は、原則として自分で「確定申告」を行い、納税する必要があります。
確定申告で損をしないためのポイントは以下の通りです。
会計ソフトを使う:青色申告であれ白色申告であれ、会計ソフトを導入するのが最も効率的です。
経費を漏れなく申告する:Webライターの仕事に関連する支出(PC代、ソフト代、通信費、書籍代、取材交通費など)は、漏れなく経費として計上します。
経費が多いほど所得は減り、税金は安くなります。
源泉徴収された金額を記録しておく:クライアントによっては、報酬を支払う際に「源泉徴収税」を天引きしている場合があります(例:10,000円の報酬に対し、1,021円が引かれて8,979円が振り込まれる)。
この天引きされた税金は「税金の前払い」です。
確定申告の際に、1年間に源泉徴収された合計額を申告することで、納めるべき税額と精算されます。
もし前払い(源泉徴収)しすぎている場合は、「還付金」としてお金が戻ってきます。
どのクライアントからいくら源泉徴収されたかを、毎月記録しておきましょう。
Webライターの現実:「やめとけ」「割に合わない」と言われる理由
ここまでWebライターの魅力や戦略を解説してきましたが、一方で、インターネット上には「Webライター やめとけ」「割に合わない」「きつい」といったネガティブな意見も溢れています。
これらは単なる噂ではなく、Webライターという仕事の「現実」の一側面を捉えています。
読者のあなたが後悔しないために、これらのネガティブな側面にこそ、誠実に向き合います。
「Webライターはやめとけ」と言われる5つの理由
なぜ「やめとけ」と言われるのか。
その理由は、Webライターという職業そのものがダメなのではなく、多くの初心者が直面する「困難」に集中しています。
理由1:報酬が低く、思ったほど稼げない(特に初期)
これが最大の理由です。
多くの人が、Webライターは「誰でも簡単に稼げる」というイメージを持って参入します。
しかし、実績もスキルもない初心者が最初に受注できるのは、クラウドソーシングの「初心者OK」案件、すなわち「文字単価0.5円」といった低単価案件です。
1記事3,000文字を必死にリサーチして書いても、報酬は1,500円。
時給換算すると、アルバイトの最低賃金を下回ることも珍しくありません。
この「始めたばかりの時期がもっともきつい」という現実を乗り越えられず、「割に合わない」と感じて辞めていく人が大半です。
対策:この記事で解説した通り、低単価ゾーンは「実績とスキルを学ぶための研修期間」と割り切り、ポートフォリオを充実させて、早期に「専門ジャンル(高単価ゾーン)」へ脱出する戦略を持つことです。
理由2:納期プレッシャーや、やり取りのストレスが大きい
Webライターは自由な働き方に見えますが、「納期」という絶対的な締め切りが存在します。
納期に追われるプレッシャーは、精神的にきついと感じる人もいます。
また、クライアントとのコミュニケーション(修正依頼、レギュレーションの解釈など)でストレスを感じることもあります。
対策:無理のないスケジュール管理を徹底すること、そして「信頼できる(=コミュニケーションが円滑な)」クライアントを選ぶことです。
理由3:悪質な(詐欺まがいの)案件に注意が必要
残念ながら、ライターを不当に扱おうとする悪質なクライアントや、詐欺まがいの案件も存在します。
(例:記事を納品したのに報酬が支払われない、テストライティングと称して無料で記事を書かせる、不当に低い単価で高難易度の作業を要求する、など)。
対策:クラウドソーシングの「仮払い」制度を利用する、契約前にクライアントの評価をしっかり確認するなど、自分の身を守る「自衛」の意識を持つことです。
理由4:初心者は仕事を見つけるのに苦戦しやすい
スキルも実績もない初心者が、最初の1件目の仕事を見つけるのは、非常に困難です。
「案件獲得が難しい」と感じ、応募(提案)を繰り返すうちに心が折れてしまうケースです。
対策:実績ゼロの初心者こそ、応募文の「量」をこなす必要があります。
初心者のうちは、10件、20件応募して1件採用されれば良い方だと割り切りましょう。
そして、その採用率を上げるために、「ポートフォリオ(サンプル記事)」をしっかり準備し、「質の高い提案文」を書く努力をすることです。
理由5:AI(人工知能)に仕事が奪われる?
近年、「AIの登場でWebライターの仕事はなくなる」という不安が広がっています。
現実:単純な情報の要約や、誰でも書ける一般的な記事の執筆は、AIに代替されていく可能性が高いです。
対策:AIには書けない「価値」を提供することです。
具体的には、あなたの「E-E-A-T(実体験)」、高度な「SEO戦略」の立案、クライアントの課題を解決する「企画力」、そして「専門知識」です。
AIを「脅威」と捉えるのではなく、リサーチや下書きを補助させる「便利なツール」として「使う側」に回ることが、これからのライターの生存戦略です。
Webライターが「きつい」「難しい」と感じる瞬間
日々の業務の中で、ライターが「きつい」と感じる具体的な瞬間は以下のようなものです。
執筆スピードが遅い:リサーチにばかり時間がかかり、なかなか執筆に進めない。
→ 対策:得意ジャンルに絞り、リサーチ時間を短縮する。
レギュレーション(マニュアル)が複雑:クライアント独自のルールが細かく、全てを守るのが難しい。
→ 対策:読解力を鍛え、不明点は納品前に質問して確認する。
フィードバック(FB)をもらうのが辛い:クライアントからの修正指示(赤入れ)が、自分自身を否定されたように感じて精神的にこたえる。
→ 対策:FBを「人格否定」ではなく、「記事を良くするための無料の指導」と捉え直す。
Webライターに向いてる人・向いていない人
こうした現実を踏まえると、Webライターには明確な向き不向きがあります。
向いてる人
・文章の「読み書き」が純粋に好き。
・地道なリサーチ(調べ物)が苦にならない、知的好奇心が強い。
・継続的に新しい知識を学ぶのが好き。
・納期やルールをきっちり守れる、責任感が強い。
・フィードバックを素直に受け入れ、改善できる。
向いていない人
・長文を読むのが苦手、活字が嫌い。
・調べ物(リサーチ)が面倒で、自分の感覚だけで文章を書きたい。
・フィードバック(修正指示)を「批判」と捉えてしまい、受け入れられない。
・すぐに(楽して)大金を稼ぎたいと思っている。
知恵袋・5ch(なんj)で見られるWebライターのリアルな評判
Yahoo!知恵袋や5ch(なんj)などのネット掲示板では、Webライターのリアルな評判が語られています。
そこでは、「単価が安すぎて割に合わない」「稼げないからやめとけ」といったネガティブな意見と、「専門性を高めれば月50万は余裕」「在宅で働けるのは最高」といったポジティブな意見が混在しています。
この差はどこから生まれるのでしょうか。
ネガティブな意見の多くは、この記事で定義した「低単価ゾーン」でのつらい体験談です。
一方で、ポジティブな意見は、その「初心者ゾーン」を戦略的に抜け出し、「専門特化」や「キャリアアップ」に成功した中級者以上のライターの意見です。
Webライターが稼げないのではなく、「戦略のないWebライターは稼げない」というのが、現実です。
(まとめ)Webライターとして成功するための最終ステップ
この記事では、Webライターの始め方から、求人・案件の探し方、収入の現実、そして専門特化による年収アップ戦略まで、あらゆる側面を徹底的に解説してきました。
最後に、Webライターとして成功するための最も重要なポイントを再確認します。
Webライターの仕事は、単なる「執筆」から「コンテンツ制作全般(SEO戦略、リサーチ、CMS入稿)」へと進化しています。
高いスキルを持つライターは、AIに代替されない専門職です。
キャリアパスは、自由な「フリーランス(副業)」だけではありません。
横浜、東京、大阪などの都市部には、年収400万〜800万円を目指せる、安定した「正社員」の求人も豊富に存在します。
収入を上げる最大の鍵は、執筆速度(1時間に何文字書けるか)ではありません。
あなたの「専門性」を高め、リサーチと執筆の「効率(時給)」を上げること、そして「SEO戦略」を理解することです。
「やめとけ」「割に合わない」と言われる理由のほとんどは、実績ゼロの「初心者(低単価)ゾーン」で直面する困難さに起因します。
その困難は、正しい戦略(ポートフォリオの作成、フィードバックの活用、専門特化)によって、必ず克服可能です。
Webライターとして成功するための一歩は、行動することから始まります。
この記事を読んだあなたが、次に取るべき「最初の一歩」は、以下の3ステップです。
ステップ1:あなたの「専門ジャンル」を決める
あなたの現在の仕事、過去の経験、保有資格、心から好きな趣味を棚卸ししてください。
ステップ2:そのジャンルで「サンプル記事」を3本書き、ポートフォリオを作成する
あなたのスキルと専門性を証明する「名刺」を作りましょう。
ステップ3:クラウドソーシングや求人サイトに登録し、応募する
そのポートフォリオを武器に、「フィードバックがもらえる案件」または「あなたの専門性を活かせる正社員・アルバイト求人」に応募してください。
本記事が、あなたのWebライターとしての一歩を踏み出すための、信頼できる羅針盤となることを願っています。

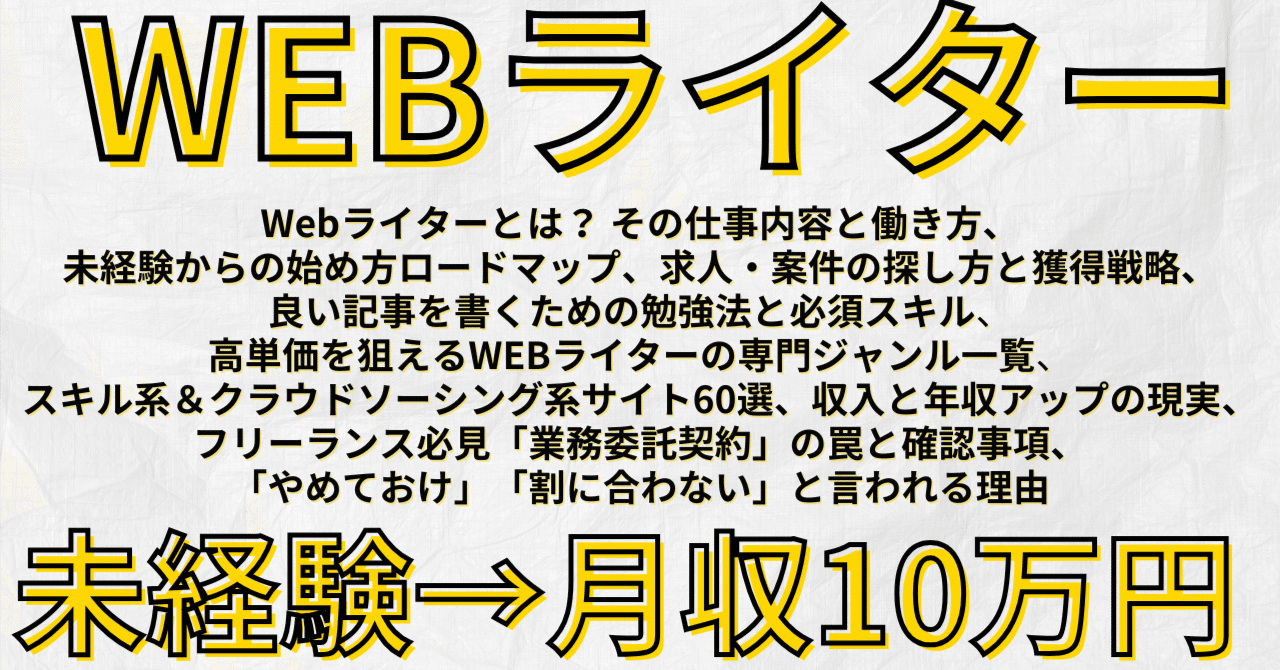
このブログだけでは話せない
インターネットビジネスで稼ぐための
ノウハウや思考、プライベート情報など
メルマガやLINE公式アカウントで配信中。
まだの場合はメルマガは
こちらからご登録下さい。
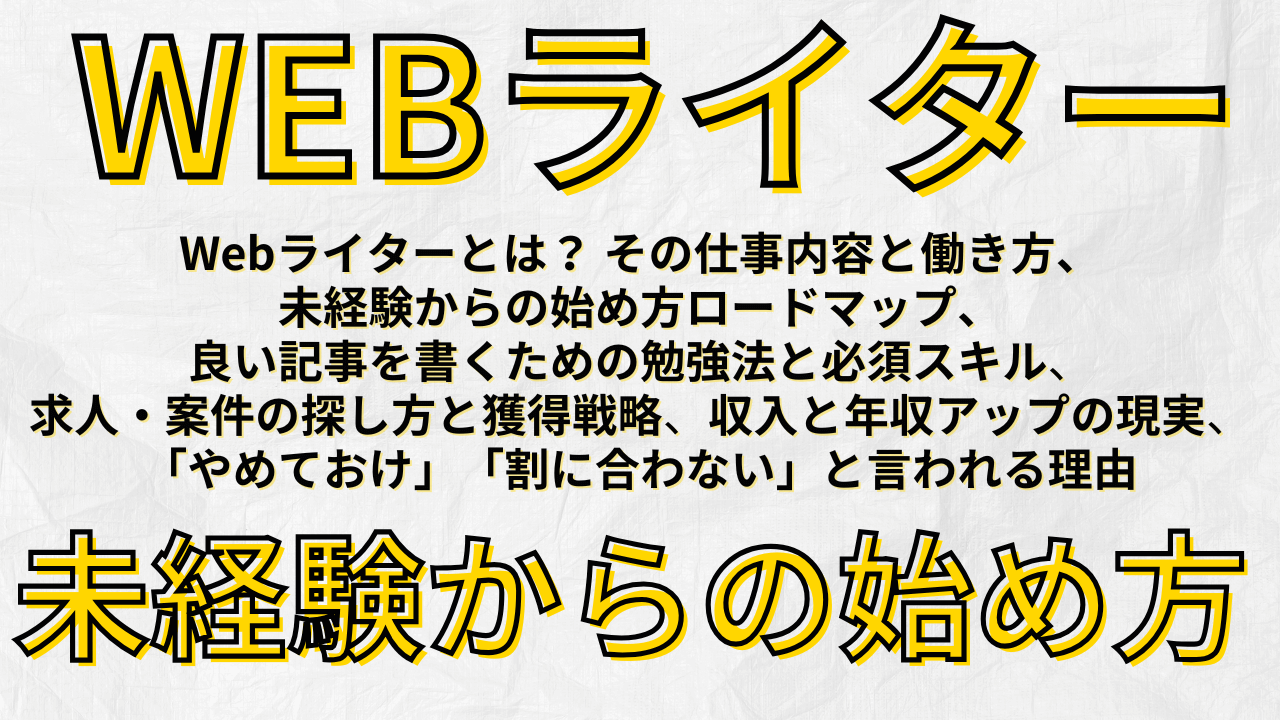
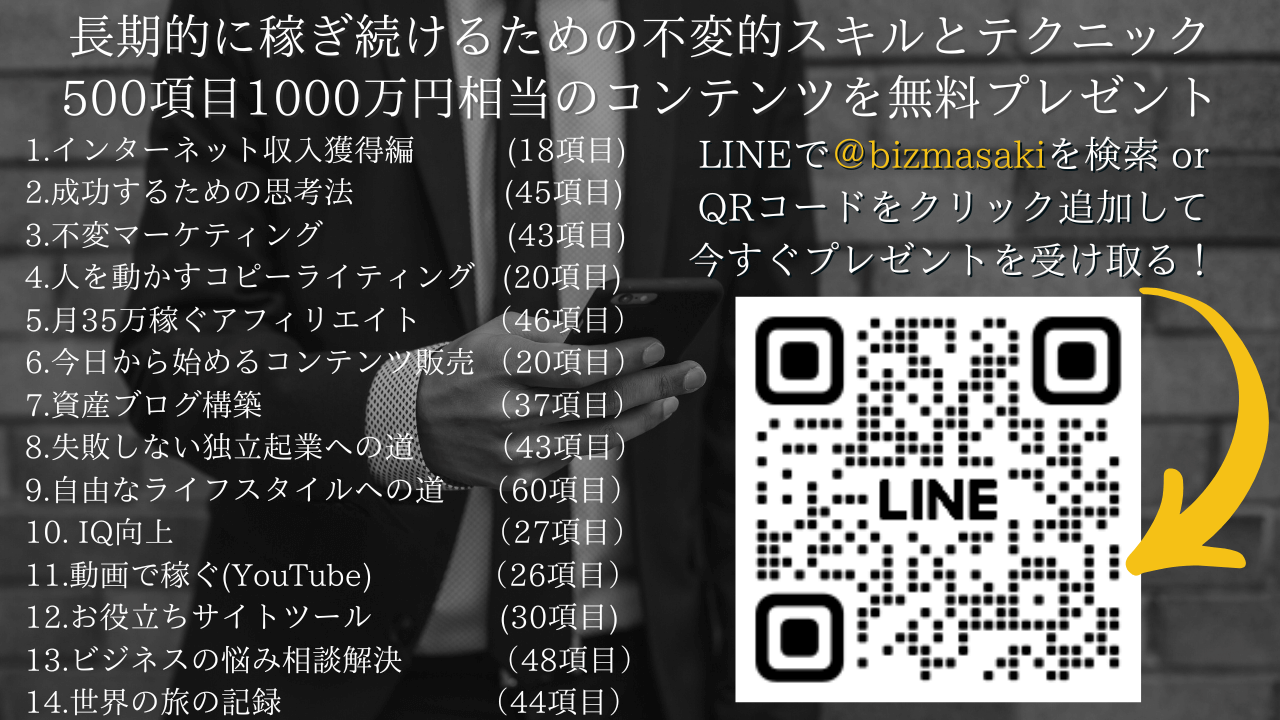




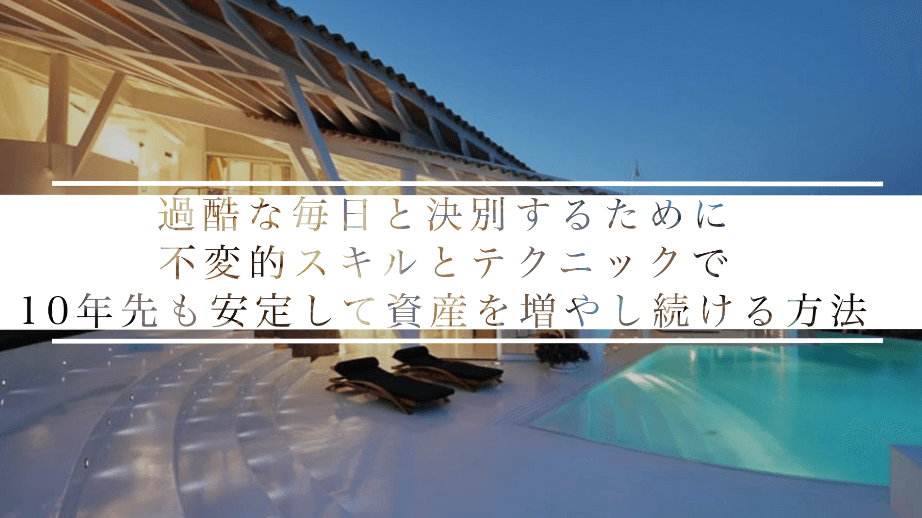
コメント